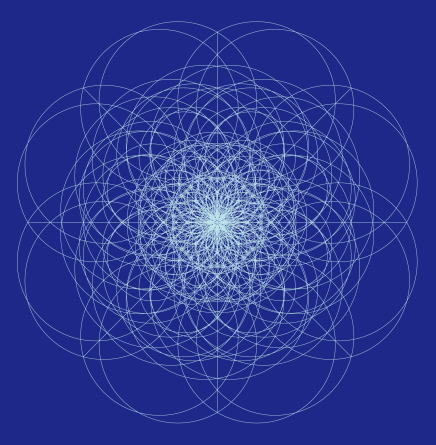四諦の内、苦集滅は釈迦が完全透視した人間生存本体の説明であり、釈迦個人はその掌握と同時に入滅することでの完結があったのであるし、本来その意向に釈迦は向かっていた。しかしその後に、釈迦は"生存(世界)の本質"に対処する"具現的な生存(域)での行動指針"たる八正道を生み出すに至った。八正道は二次的に釈迦が考えたところの「生存の本質(苦集滅)に添いながらもなお現実的に生存することを可能とする方法(補足1)」である。
あるいは言い換えるならば、"釈迦は生存の本質(苦集滅)の掌握と共にそれでも生存を維持することの合理的な方法(生存すべきを支持する何らかの意義)"というものがあること(あり得ること)を見出したということである。(補足2)
あるいはまた、こうも考えなければならないのではないか。つまり、もし人が生存の本質(苦集滅)を完全に把握したならば、その人はそこで完結を選ぶ。だが釈迦だけはそれを成さず、その代わりに苦集滅に対し現実的生存側から拮抗すべく八正道という方法を生み出し、それを実践することで「生存の本質(苦集滅)を 把握しながらのクリティカルな局面でのぎりぎりの生存(域)」というものが人類にとってあり得ると考えた。(補足3)
これが現在自分が思 うところのガイドラインである。これは大乗を考える上で、当然この基本が無ければ大乗が成り立たないことにも関わる。大乗はこの釈迦思想側の基盤を、彼らが所持する全く異なる世界像になんとか重ねて壮大に拡張しているのである。釈迦の八正道の本質は苦集滅の絶対性に対する僅かの生存側への差異であり、その実践による効果としての遅延である。その遅延が生存となる(その遅延により生存が起こる)。勿論、衆生には元々生存の本質(苦集滅)の掌握は無いので、釈迦とは異なり八正道は現実的な生存の形式として現れる。釈迦は衆生にそのように示したのである。思うにこれが大悲の本質である(補足4)。
またこうも考えるべきではないか。もし人が苦集滅を掌握したとして、その時にまた現実的生存側に戻ることがあるとしても、釈迦のように衆生総体に対応できるような何らかの合理的な方法論を生み出すことは困難だろうということ。まずそのような人は把握した内容を語ろうとしなかったり、一旦思ったとしてもそれを衆生の理解力に合わせて語ることのあまりの困難さに熱意を維持できないだろう(実際釈迦自身も最初にそう考えたのである)。自分は釈迦思想が特別(特殊) である要所をここに思うのである。
------------------------------------------------------------
[補足1] 釈迦にとっては選択的であり、衆生にとっては唯一の。
[補足2] 釈迦自身にとっては本来この必要性は無い。衆生にとってはこの方法によらなければ苦集滅の掌握に至る道はない。八正道とは(人間的に再来した)釈迦が、衆生の能力に沿わせ編成したものというべきであろう。
[補足3] 意図してここで津田真一先生の用語を選ぶ。
[メモ] 津田真一先生指摘(反密教学)に関わり: 現法的梵行の「現法的/drstadharme」の意味は「この現在世のなかで」だという。これは、完結する苦集滅に拮抗し、なお生存が「八正道=梵行」というあり方をもって成される場合、その時、苦集滅の完結性絶対性に対する遅延として生存は"意義化"され、それは(本質が苦集滅たる)現在世での事がら (法)として衆生に現れている、とも書きうるところの内容に絡む。要するに、梵行とは現世生存での苦集滅の転移であり、苦集滅の遅延的具現である、と。なぜそうなるのかが重大であろう。梵行の結果、生命は受け継がれない。現世にとどまった一定の遅延の後に何も残さず滅に帰結(入滅)するのだから、やはりその者は苦集の総体に因を残さないだろう、ということか?
[補足4] 津田真一「反密教学」-Ⅱ釈尊の宗教と華厳- を確認再読したところ、結局ここで延々書いていることの基幹はこれにあり、当追跡調査も紆余曲折経た結果、凡庸な頭でも多少理解が及んできたという話であった。以下同書より引用
釈尊はこの境位で停ってしまってもよかった。彼は<女性単数のdharma>の明の極に於いて安住し、その存在の高みから「諸法」、即ち存在者 の位層の諸相を観照し、「解脱の楽しみ」のうちに一人の独覚者(pratyekabuddha)としての生を終えてもよかったのである。しかし、彼はそこに停らず、無明を脱して明に至らんとする反自然的ヴェクトルのペルソナである梵天の勧請という神話が象徴する如く、釈尊自身の瑜伽の体験にとっては外的と なる、慈悲という原理を採択することによって、説法の決心をする。(80P)